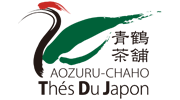日本茶の種類
いざ日本茶の世界に取り組もうとすると、最初はその広大さに気おくれしてしまうかもしれません。多様なお茶の種類や、しばしばいい加減に名付けられている商品名などに圧倒され、どこから始めたらいいのか分からなくなることもあるでしょう。このページでは、様々な種類の日本茶についてお話しするところから始め、この複雑に思える日本茶の世界を理解するために不可欠な羅針盤となる知識をご説明します。なおここでは、チャノキ(Camellia sinensis)の葉から作られる狭義の「お茶」についてのみ説明し、一般に茶外茶と呼ばれる麦茶やそば茶のような他の植物のお茶は扱いません。
日本茶とは?
日本で生産されるお茶は、99%が緑茶、つまり茶葉を酸化させずに作るお茶です。一方、紅茶や烏龍茶は、その製造に茶葉を酸化させる工程を含みます(この「酸化」はかつて「発酵」と混同されていたため、現在もしばしば「発酵」または「酸化発酵」と呼ばれます)。緑茶の場合、茶葉が酸化しないよう収穫直後に加熱して酸化酵素の働きを止める必要があります。この加熱を「殺青(さっせい)」と呼びます。世界で最も一般的な殺青方法は「釜炒り」と呼ばれるやり方で、生の茶葉を高温の鉄鍋等で直に加熱します。しかし、殺青方法は釜炒りだけではありません。現在では非常に稀ですが「煮る」方法、そして蒸気を使って「蒸す」方法です。
このうち日本で主流の殺青方法は「蒸し」です。煎茶、玉露、かぶせ茶、玉緑茶、そして抹茶(碾茶)など、ほとんどの日本の緑茶は蒸して作られています。生産量は非常に少ないですが、釜炒り茶だけが「釜炒り」製法で作られるお茶です。
蒸し製法は理論上、非常に速く効率的に多くの茶葉を処理できるという利点があります。水蒸気が生の茶葉と接触する瞬間に水に変化し、その状態変化が非常に大きな熱エネルギーを生みます。同時に、茶葉の中の酸化酵素は熱によって完全に働きを止めるのです。このように見てみると、日本の緑茶の特徴は「蒸し製であること」と言えるでしょう。
最後に、日本における茶の歴史は8世紀までさかのぼることができますが、今日私たちが知っているようなお茶の開発や発展はごく最近のことで、19世紀に「宇治製法」と呼ばれる製法が一般化したことがその始まりです。宇治製法は蒸した茶葉を揉む特殊な製法で、1738年に永谷宗円によって開発されました(当時すでに、宇治製法とは異なるやり方の蒸し製のお茶や、揉んで作るタイプのお茶もまた存在していました)。しかし何よりも重要なのは、19世紀半ばにアメリカからの輸出需要にこたえる形で、静岡で宇治製法が進化をとげたことです。さらに手揉みだった宇治製法は、19世紀後半から20世紀前半にかけて製茶機械により並外れた精度と効率性で模倣されることとなります。このように、日本茶はかつてないほどの機械化の進展により、手揉みの品質を凌駕するほど進歩したという点においても特徴的です。
煎茶
煎茶は2019年の日本の荒茶生産量のうち、実に53%を占めます。この数字は少ないように思えるかもしれませんが、これは総生産量に占める割合、つまりしばしばほうじ茶やペットボトルの原料となる低品質の番茶も含めた中での比率なので、あくまでも相対的に捉える必要があります。一方で、高品質な茶葉が得られる春の初摘み(一番茶)だけに限れば煎茶の割合はぐっと高くなり、約75%を誇ります。つまり煎茶は、日本茶の世界の探求を始める上で欠かせないジャンルであるだけでなく、その多様性と豊かさゆえに、日本茶への知識を深めていくうえで常に重要な立ち位置にあると言えるでしょう。
摘み取った茶葉はまずすみやかに蒸し、次いで揉むことで水分を少しずつ茶葉の外に出していき、最後に加熱して乾燥させます。揉む工程をまとめて「揉捻(じゅうねん)工程」と呼び、煎茶の場合は4段階あります。1.粗揉(そじゅう;熱風を当てながら揉む)、2. 揉捻(じゅうねん;熱を加えず、加圧しながら円を描くように揉み水分の分布を均一化する)、3.中揉(再度熱風を当てながら水分を揉み出し乾かす)、4.精揉(加温しながら揉み、乾燥させ形を整える)です。
4段階の揉捻工程ののち、茶葉は乾燥機にかけられ、水分が5%程度残った荒茶(あらちゃ)が出来上がります。荒茶は飲むことができ、仕入時の拝見(テイスティング)にも使われますが、いまだ完成品ではありません。荒茶から茎や粉末を取り除き、様々な大きさの茶葉をふるい分けて大きな葉を切断し、「火入れ」と呼ばれる最後の乾燥工程で水分含有量を約3%まで下げます。この一連の仕上げ工程を経てはじめて、茶葉が最終製品となります。
現在、煎茶には大きく分けて2種類あります。標準的な蒸し時間の「普通蒸し煎茶」と、1950年代に発明された比較的新しい蒸し方の「深蒸し煎茶」です。「深蒸し煎茶」は「普通蒸し煎茶」の約二倍以上という長い蒸し時間の煎茶を指します。
「浅蒸し(普通蒸しと同義)」、そして「中蒸し(中程度の蒸し時間)」あるいは「特蒸し(特に長く蒸したもの)」など様々な呼び方が見受けられますが、これらには明確な基準がありません。日本茶業中央会などの関係機関では現在「煎茶」「深蒸し煎茶」と呼んでいます。
被覆とは?
従来、煎茶は露地栽培を基本とするお茶でした。しかし近年、より旨味が強く、より緑色の濃いお茶の需要に応えるため、多くの煎茶が期間の長短はあれど収穫前にカバーをかける被覆栽培で育てられています。(被覆栽培については「玉露」の項で説明します)。
最後に、栽培品種(ワインでいうメルローやカベルネ・ソーヴィニョン、お米でいうコシヒカリやゆめぴりかなどに相当します)の多様性が、煎茶という豊かな香りを持つカテゴリーにさらに奥行きを与えています。また「煎茶」というカテゴリーの中には全く香りが異なるお茶が同居していますが、値段の面においても安価なものから最高級品まで非常に幅広いです。
玉露
玉露はハイクラスなお茶と思われがちですが、必ずしもそうとは言えません。なぜなら玉露の中にも実に様々な品質、価格のものがあるからです。また、煎茶と比較してより優れたお茶であるというイメージも根強くあります。しかし、これは全くの誤解です。玉露は煎茶とは全く異なる種類の緑茶であり、特に飲み方が大きく異なるため、けっしてレベルの上下という観点で比較すべきものではないのです。
玉露の特徴は、被覆栽培の茶葉から作られることです。茶樹は収穫予定日の少なくとも20日前から覆われ、ときには40日以上も被覆されます。しかし、収穫した後の製造工程は煎茶とほとんど変わりません。しかし、玉露には被覆方法と摘み方がそれぞれ数パターンあり、それらが最終的な品質を大きく左右するということを理解しておくことが重要です。
被覆方法と摘採方法の種類
●自然仕立て茶園・棚がけ/手摘み
最も伝統的で、最もハイレベルな玉露を作るための方法です。 茶樹は一般的な茶畑のようにかまぼこ型に刈り込むことをせずに伸ばします。一本一本の枝の長さに差が出るので、摘採方法は必然的に手摘みとなります。また収穫後、茶樹を非常に低く刈り込み、1年間かけて再び伸びるのを待ちます。そのため、収穫は年に一度のみです。このタイプの茶園は、藤棚のような棚を設け、その棚に被覆材をかけることで日陰を作る「棚がけ」と呼ばれる方法で日陰を作ります。棚がけは葦簀(よしず)や藁など天然素材のものや、化学繊維製のものがあります。これらの被覆材は二重、三重に重ねることができ、それによって遮光率のコントロールをしています。
●通常の茶園(はさみ摘み仕立て)
ごく一般的なかまぼこ型に刈り込んだ茶園では、被覆方法と摘採方法の組合せにいくつかのパターンが考えられます。
・棚がけ/手摘み
・棚がけ/機械摘み
・直がけ*/機械摘み
*直がけ:茶樹を直接合成繊維製のカバーで覆う被覆方法。煎茶の被覆方法としては主流。
なぜ被覆栽培をするのか?
被覆栽培は、うま味成分を多く含む茶葉を作るために行われます。茶樹は土壌から根を通して窒素化合物を吸収し、うま味成分のアミノ酸を生成します。しかし茶樹に日光が当たると、これらのアミノ酸は、葉の中で光合成により渋み成分であるポリフェノールに変換され、減少します。遮光することでこのプロセスがゆるやかになり、より多くのうま味が保持されます。さらに、遮光はカフェインの分解も遅らせるため、被覆栽培のお茶はカフェインをより多く含みます。
玉露はポリフェノールの渋味を抑えつつ、その凝縮されたような強いうま味を引き出して味わうために、たっぷりの葉と驚くほど少ない低温の湯で非常に濃く抽出します。濃厚なエキスを味わうという意味では、“日本茶のエスプレッソ”とも言えるでしょう。
玉露は伝統的に京都(宇治)で生産されていますが、福岡県の八女玉露が、京都とはやや異なるスタイルで品評会のトップに立っています。生産量はわずかですが、静岡県産の朝比奈玉露もあります。
碾茶/抹茶
誰もが知っている抹茶ですが、原料となるお茶を碾茶(てんちゃ)と呼びます。碾茶を石臼などで挽いて粉にしたものが抹茶です。日常的に飲むことはほとんどないにも関わらず、1990年代以降に生産量が飛躍的に増加した唯一の日本茶です。ただし、この伸びは主に製菓用や抹茶ラテ用の低品質、または平均的な抹茶の増加によるものであることを理解し、心に留めておく必要があります。
元来、抹茶は自然仕立て茶園で被覆栽培した(玉露の項を参照)茶葉を蒸したのち、揉まずに碾茶炉(てんちゃろ)という炉で乾燥させ、石臼で挽いたものです。正確な統計はありませんが、もっとも丁寧に作られたこのタイプの抹茶は、世界で販売されている日本産抹茶のわずか3%程度であると推定されます。 また摘採に関しても玉露と同様にいくつかのバリエーションが存在し、それぞれ碾茶の品質に影響します。摘採方法の違いもさることながら、摘採時期に関しても二番茶から作ったものや、さらに残念なことに「秋碾(あきてん)」と呼ばれる、遮光さえされていない秋摘みの碾茶も存在します。粉砕方法も非常に大切なポイントで、最も安価な抹茶は石臼ではなくセラミック製のボールミルで挽かれるため、粒度が粗くなります。
抹茶は1191年に入唐僧の栄西によって中国からもたらされたと伝えられていますが、当時の茶園は覆いをしていない露地の茶園でした。被覆栽培が始まったのは、16世紀ごろだと考えられます。 伝統的に京都で生産されていますが、愛知県西尾市が業務用抹茶の生産地として大きな存在感を示しています。
碾茶の製造上の特徴は、葉を蒸したあと揉まずに煉瓦造りの大きな炉(碾茶炉)で乾燥させることです。より簡素な炉(簡易炉)もあり、こちらは低価格帯の製品を作るときに使用されます。
なお、抹茶には明確な等級はありません。海外でよく使われる「セレモニーグレード」という概念は日本には存在せず、この言葉自体が欧米の販売業者によって考案されたものです。もしどのような抹茶か知りたい場合には、販売店に取り扱っている抹茶の産地・収穫時期・茶園の仕立て・被覆の方法と期間・石臼挽きか粉砕機による粉砕か、などについてたずねてみると良いでしょう。すべてはわからないかもしれませんが、選ぶ際のヒントになりえます。
最後に…、玉露と同様、抹茶には「新茶」という概念はありません。これらのお茶は、楽しむ前に熟成させる必要があるからです。そのため、その年の春摘みの抹茶は秋以降に売り出されるのが一般的です。熟成期間は碾茶のまま保存され、ほどよく熟成したところで挽いて抹茶にしたものが出荷されます。伝統的な産地の宇治では、1年間熟成させる必要があると考える人もいます。
かぶせ茶
かぶせ茶はその名の通り、茶葉に「覆いをかぶせて育てた」緑茶です。玉露や碾茶とは異なり、ほとんどの場合「直がけ」と呼ばれる被覆材を直接かける方法で栽培されます。被覆期間は玉露よりも短いですが、煎茶よりは長く、おおむね2週間程度です。京都府と三重県が主産地で、摘んだ後の製造方法は煎茶と同じです。
玉緑茶(蒸し製)
「玉緑茶」はヨーロッパのお茶好きの方の間では比較的知られている名前ですが、実は日本ではかなりマイナーなお茶です。
玉緑茶と呼ばれるお茶には、蒸し製のものと次項で紹介する釜炒り製(釜炒り茶。中国のように釜で炒って作る緑茶)のものがありますが、単に「玉緑茶」といった場合、この蒸し製玉緑茶を指します。
今まで紹介してきた日本の緑茶と同様に蒸して作られますが、玉緑茶は揉捻工程と乾燥方法が煎茶をはじめとした他の緑茶とは少し異なります。最後の揉捻工程である「精揉(せいじゅう)」を省略するため、できあがった茶葉は煎茶のような針状にはならず、勾玉状にカールしています。この外観から、「グリ茶」と呼ばれることもあります。
また、揉捻の工程が一段階少ないぶんきちんと乾燥させる必要があり、乾燥工程は水乾機と再乾機という機械を使った二段階になっています。
この玉緑茶の製法は1920年代、蒸し製法用の既存の設備を活用しつつ、中国の釜炒り製緑茶に似たお茶をつくることを目的として開発されました。当時はソ連を経由して中東や北アフリカへ輸出するために、中国緑茶とブレンドできる茶葉が求められていたためです。
現在では、主に佐賀県の嬉野、長崎県の彼杵、熊本県で生産されており、煎茶と同様に深蒸しにしたものや被覆栽培のものも増えています。乾燥工程が多いことで香ばしく温かく甘い香りを持つことが多く、被覆によるうま味とあいまって、とても飲みやすいお茶となっています。
釜炒り茶
緑茶の最後は煎茶よりも古く17世紀に中国から伝えられた、生葉を高温の表面で加熱して酸化を止め、揉みながら乾燥させる方法で作られる釜炒り茶です。この製法は19世紀に蒸し製法にとってかわられ、今日では非常に少なくなっています。
主に九州の宮崎県と熊本県で生産されています。渋みは少なく、香ばしさが際立ちとても香りのよいお茶です。日本でもあまり知られていませんが、気軽に試すことのできるお茶です。
紅茶と烏龍茶
驚かれるかもしれませんが、日本では19世紀後半から紅茶を生産しています。茶業界が西洋向け煎茶の輸出で大いに発展すると、政府は外国市場向けの紅茶生産も展開することに決めました。ですがそうした努力にもかかわらず、この計画が成功することはなく、1970年代初めには紅茶生産は完全に姿を消しました。 1980年代になると、熱心な数人の生産者の方々により少しずつ紅茶生産が再び始められ、注目されるようになり、2010年代からは品質も格段に良くなりました。紅茶生産は日本の茶生産全体からみるとまだほんのわずかかもしれませんが、次第に関心が高まり、青鶴茶舗- Thés du Japonも最高の紅茶をお届けしたいと努めています。
政府が紅茶生産を奨励した時期の品種がいくつか残っています。1878年に多田元吉氏が日本に持ち帰ったインド系実生から選抜された最も古い紅茶用品種べにほまれや、べにひかり、最も広まった一番新しいべにふうきなどです。 また、いずみや香駿など緑茶用品種で作られたすばらしい紅茶もあります。 現在、日本の国産紅茶は「和紅茶あるいは「地紅茶」とも呼ばれています。
紅茶は緑茶と同じ茶葉から作られていますが、製造方法が異なります。葉を、通常言われるところの「発酵」をさせますが、実際は発酵作用ではなく酸化のことです。摘み取った葉は萎凋して揉捻してから酸化させます。最後に酸化を止めて乾燥させるために熱を加えます(この後にさらなる焙煎工程があることもあります)。
烏龍茶も生産されていますが、まだ少ないですし、まだまだ進歩の余地があります。
番茶
番茶とは一つのお茶ではなく、いろいろなものがあります。 番茶と言われるもので一番多いのが、遅くに摘み取られた粗い煎茶のことです。秋摘みの葉(秋冬番茶)や一番茶の後の遅摘みの厚い葉(刈番ということも)のお茶です。
ですが、番茶という言葉は地方の伝統的なお茶の種類を指すこともあり、その製法は実に様々です(葉を煮て天日で干すだけ、葉を微生物発酵させるなど)。今では希少になってしまいましたが、食事と深く結びついた普段の大衆向けのお茶です。普通の日本人が飲むお茶といえば、戦後までは煎茶でも、まして抹茶でもなく、番茶でした。京番茶、美作番茶、碁石茶などがあります。
その他のお茶
以下でご紹介するお茶は、これまでに説明したお茶の形が変わったもので、ジャンルの違うお茶になります。
●ほうじ茶
一般的に低品質の緑茶を高温で焙じたお茶
●玄米茶
一般的に低品質の煎茶や番茶に炒った米を加えたお茶
●茎茶
お茶の樹の茎は仕上げ段階で分別されて茎茶として売られたり、ほうじ茶の原料に使われたりします。
茎茶は「出物」と呼ばれるお茶です。
●粉茶
これも出物で、荒茶の仕上げ時に分別される粉末のお茶です。
●芽茶
これも出物で、荒茶を仕上げる時に分別された新芽の小片のお茶です。
●粉末茶
粉末状にした緑茶のことですが、抹茶のことではありません。原料となるお茶はとてもレベルの低いお茶で、粉末にする方法も異なります(フリーズドライなど)。一般にインスタント緑茶として知られ、ほとんどのすし屋では粉茶ではなく粉末茶が使われるようになっています。